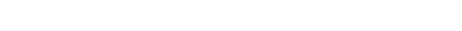[INTERVIEW]
インターネットの
次の10年を
思いっきり語る
村井純教授
日本のインターネットが産声を上げたのは、1984 年の東工大-慶応大でのUUCP 実験だ。本格的に商用化されたのは、ISP サービスが立ち上がった1994 年。これまで、日本のインターネットのほとんどの進化の場面に立ち会ってリードしてきたのが、村井教授である。
インターネットは今、メールとWWW 利用という第一期工事を済ませ、IP 電話に代表されるリアルタイム情報を支えるインフラとして第二期工事に入り始めている。その節目にあたる今、今後のインターネットに求められるもの、我々に与えてくれる力など、インターネットの次の10 年を、村井教授に思いっきり語ってもらった。
聞き手:本誌編集長
Photo:津島隆雄
音声や映像をインタラクティブに扱うためには、今のインターネットはまだ20 %の段階
――1994 年の本誌創刊時に「10 年後のインターネットはどうなりますか?」と伺いましたが、今回はさらに次の10 年について伺います。
まず最初に、現在のインターネットは、村井先生の理想の何パーセントくらいを実現できた段階なのでしょうか?
●多分20 パーセントくらいですね。ただ、インターネットはある水準まで「完成した」と感じている人は多いでしょう。それは、電子メールとWWW の普及が大きな要因です。これらができたことで、コミュニケーションに衝撃的な変革がもたらされ、「インターネットは凄い」と思われるようになったわけです。そういう意味でのインターネットの第一期完成は、2000年頃だと言えますね。
今は、ブロードバンドができ始めた段階で、「速いインターネット」がちょうど始まったばかりなのです。
ブロードバンドで何ができるのかに関してはまだまだ課題がありますが、少なくともストリームのコンテンツがビジネスになることはわかってきて、徐々に放送の足回りにも使われ始めています。また、P2P やテレビ会議・電話もできるようになってきました。こういうリアルタイムメディアの基盤となれるかが、ブロードバンド、つまり新しいインターネットの力の見せ所だと思っています。まだまだ、一般の人のものにはなっていないところがありますが。
――速いインターネットを実感できるサービスが不十分だということですか?
●そうです。今は、多くの人が「テレビ電話」というとFOMA のことだと思っています。インターネットが映像と音声をインタラクティブに扱うものだとすれば、まだ20 パーセントにも達していないと思うのです。
放送と通信が融合すると、クリエーターの自由度が増え、コンテンツマーケットが拡大する
――放送とインターネットが結びついたとき、放送はどうなると思いますか?
●2つの、全然違う視点があると思うのです。
1 つは、今の放送コンテンツがインターネットでどう配信されるのか、また、どのように変わっていくのかという視点です。
これは「放送と通信の融合」などといわれますが、基本的にはコンテンツを作る人やそこから情報を得て楽しむ人、そういう人たちの可能性や自由度が上がるので、その結果コンテンツのクオリティーが上り、マーケットが拡大し、良質のコンテンツが生まれる方向へシフトしていくと思います。
テレビの電波をIP で使うと、放送以外の多様なコンテンツで共有できる

●そしてもう1 つは、純粋に技術的な話として、放送メディアがデジタル化されてきたおかげで、その配信の仕組みを使うと放送以外のデジタル情報が一対大多数で共有できるのではないか、という視点です。
デジタル化された放送の足回りを、インターネットがどう使って強いインフラストラクチャーにできるかという意味です。大規模なコンテンツの同時受信を考えるときは、インフラを上手に使い分けることが重要です。大容量のデータをみんなで共有する場合は、放送の足回りを使えることになれば、今の放送コンテンツだけでなく、教育、出版や緊急時の情報などを共有するのが簡単になるでしょう。
――たとえば、東京タワーからの電波をIP化するということですか?
●テレビのための電波を使うのはライセンスで決まっているので、今は不可能でしょう。しかし、そういった制限を一切忘れて、13 セグメント、5.6MHz の周波数にデジタルデータを載せると考えると、さまざまなことが可能になります。
SKY PerfecTV はKu バンドで放送電波にIP を載せる実験をやりました。エンカプセレーションといいますが、IP のデジタルデータをMPEG エンコーディングし、それを映像として放送の送信機から送信し、今度は受信機が映像としてそれを受けて、その映像をデコードするとIPのデータが出てくるというものです。
地上波デジタルも基本的にはデジタルデータを送っているので、エンカプセレーションしたIP を送受信するソフトウェアを作れば、すぐにIP の送受信が可能になるわけです。
つまり、放送局はすべての放送を変更して、IP を通す土管業者に生まれ変わるということが、技術的には可能なのです。
日本はテレビとラジオの放送技術が同じ形式なので、これができればテレビは自由に放送コンテンツを流して、ラジオはIP を使って新しいサービスモデルを生み出すということも不可能ではないのです。
現在のライセンス的にはありえないことかもしれませんが、技術的には地域単位で圧倒的な数にIP を送信する試験を絶対に行っておくべきでしょう。
――その足枷になっているのは、電波の割り当て政策ですか?
●いえ、そうは言えません。実際に、その技術が有効かどうかもまだ実証できていません。この実験については、今年にも行いたいと思っています。
問題はラジオやテレビの電波割り当ての免許が、利用法とセットだということです。別の使い方を実験できる特区政策のようなものを作って、使ってみることはできないかと思っています。
韓国では済州島で電波の実験利用を特区政策としてやっており、新しいメディアの電波利用はそこで実験されているのです。日本もそういうことをやれるといいのですが。
ケータイは、未来のノードに対するプロトタイプ

――インターネットから見たとき、ケータイにはどのような役割を期待されているのでしょうか?
●以前、ケータイは「本物のインターネットじゃない」という見方があったと思います。しかしそれは今、大きく変化しています。
理由の1 つは、センサネットやIC タグのようにノンPC デバイスがインターネットにつながったときの役割が検討され始めているからです。これらは、インターネットにおける中継ノードとしての役割はないのですが、エンドシステム、エンドデバイスであり、インターネットの一人前のノードとして、きちんと認識されるようになってきたのです。
もう1 つはコンテンツの知的所有権の問題です。DRM(デジタル知的所有権管理)によるマネジメントを模索していったとき、ケータイはその際の安心感を先に作ったという経緯があり、エンドデバイスの先駆モデルとしての役割があります。
権利とコンテンツがどの程度自由になるべきかという問題はありますが、きちんとコントロールできた成功例として、大変意義があると思います。
――それはi モードのことですか?
●そうです。i モードはインターネット上のサービスですからね。ケータイをインターネットのノードの1 つとして、再定義しないといけないと思います。
それからもう1 つは、携帯できるデバイスのプロトタイプとしての意義が大きい。腕時計やメガネ並みに、「ケータイを持ち歩いています」ということが当たり前になってきました。
今のケータイは、Java が載ってプログラマブルになり、位置情報が読め、写真が撮れ、いいディスプレイにスピーカーまで付いています。ここまで進化してくると、ケータイで新しいクリエイティビティーを実現していくことは、かなりおもしろいことになってきましたね。
「電話の世界の残党」といった位置からスタートして、今は凄く市民権を持った1つの未来のノードに対するプロトタイプという位置づけになっていると思います。
ケータイは、新しい人が新しいものを自由に作り出せるプラットフォーム

●ケータイは、新しいアイデアを持った人たちが、自由に新しいものを作り出せる環境になり始めています。
たとえば、ドコモの「お財布ケータイ」のSDK(開発キット)は、インターネット側ではIP を話せて、ケータイからは位置情報を入手でき、フェリカのメモリーに読み書きできます。もちろん課金情報などを勝手に書き換えられては困るので、制限は加えてあるのですが。一応すべてのプログラマブルなインターフェイスを持っているのです。
KDDI が発表したRFID タグリーダ搭載ケータイの試作機は、SD カードのインターフェイスを使っています。SD カードのコネクターを利用してローディングモジュールをいろいろと付けられるのです。すると、PC カードのようにSD カードのインターフェイスを持っている限り、どんなデバイスも接続できるようになります。
皆が持っているケータイで、このような自由な発想の開発が可能になってくると、プラットフォームとして非常におもしろいですね。
――ケータイがオープン化していますね。
●そうですね。ドコモのケータイでは、802.11 でも通信できるものがあります。今後のケータイは、802.11 とパケットのデュアルフォームのデバイスが常識になってくるでしょう。
IC タグの発展には「洗練された抽象化できる空間を作る」ことが必要
――IC タグとインターネットの未来について教えてください。
●日本で言うユビキタスコンピューティングの話になりますが、実空間の中の物を識別する、物の知識を得るようなネットワークができなければならないでしょう。
識別子(ID)の話は「選挙」に例えることができます。選挙では、1 人1 つの選挙権を持っていることを厳格に制御し、そして誰が誰に投票したかはわからないというシステムが必要になります。それには、きちんとしたID を制御できる空間と、プライバシーを守って匿名性を作り出す仕組みが両立しなければなりません。それが可能になれば、無限の可能性があるわけです。そのためには、「洗練された抽象化できる空間を作り出す」ことが必要なのです。
今、RFID を使えば、目の不自由な方が動きやすい空間を作ることや、物流のサポートなどができるでしょう。それらの経験を蓄積していき、本質である「識別子が存在し、それがネットワーク上で結びつく」世界を広げていかなければなりません。
日本の本当の強みは、「物作り」より「ユーザーの使いこなし力」
――実空間を把握するためにはある程度の数が必要ですが、どうしたらそのような環境ができるのでしょうか?
●僕は、日本の環境は世界一だと思いますね。
たとえば、RFID で期待されているのは、物流でトレーサビリティーのために利用するというモデルです。でもこれは、むしろ関心が低くて、結局どの倉庫でもできればいいに決まっているという感覚です。一番利用すべきであろう飛行機の荷物だって、バーコードがかなり実効的になっています。
ところが、そんなこと以上にこの国の凄いところは、ケータイというパッシブICタグの、リーダー・ライターをすでに持っているということです。フェリカのリーダーだって、コンビニで1500 円で売っています。あれを使えば、人のお財布の中身や、Suica で昨日どこに行ったかまでわかるのです。これは凄い。リーダー・ライターを、これだけ個人が持っている国はありません。それをドコモのケータイのみならず、au もやってしまうのですから。
日本の恐ろしいところは、コンシュマーがすでに巷にデバイスを持っていることです。世界より3 歩くらい早いと思いますよ。
つまり、「使いこなし力」が高いのです。技術の発展において、やはり最後に求められるのはユーザーの能力です。日本人はそれが高いから、そこから生まれる新しい問題解決の意味は大きいのではないでしょうか。経済誌の議論では、「日本の強みは物作りの力」などと言われますが、僕は必ずしもそう思わない。IT 機器に関しては使いこなす力が圧倒的に強い。新し物好きだし、バリバリ使いますしね。
ディペンダブルインターネットはISP に創ってほしい
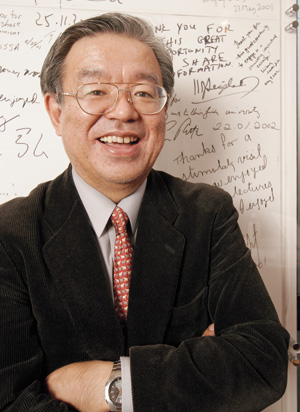
――WIDE のテーマとして、「ディペンダブルインターネット」と「アドホックネットワーク」を取り上げておられますが?
●いまインターネットに求められるものは、「知識のある人が使いこなす環境」から「誰でも安心して使える環境」に変わりつつあります。その新しい要求に応えられるネットワークがディペンダブルインターネットです。
アドホックネットワークは車車間通信など、物理的に近づいたものがアクセスポイントを必要とせずに構成していくネットワークのことです。
――ディペンダブルインターネットは、誰が作るべきなのでしょうか?
●それは、やはりISP だと思うのです。その足回りをどう敷設するのかはわかりませんが、時代とマーケットが解決していくことではないでしょうか。
IPv6 の意義は、Skype がやっていることを誰でもできるようにすること
――Skype が登場してP2P で電話が可能なら、IPv6 でなくともIPv4 でいいのではないかという意見もありますが?
●それは、v4 かv6 かというよりは、NATに頼るか頼らないかということですね。v4 というのは43 億個しかグローバルアドレスがないわけですから、どこかでスモールグループを作る必要があります。しかし、それはグローバルに使えるアプリケーションの発展を阻害することになります。Skype は、v4 で動かすためにソフトウェアでもの凄い苦労をしているのです。
それとさっきの選挙の問題です。つまり、識別子を持っている環境で自由にコミュニケーションができることを前提に、どこまで実現可能なアーキテクチャーを提供できるかという問題なのです。つまり、Skype ができることと同じことを、誰でも創造的に開発できるようにしていくことが、真のv6 の世界なのです。
Skype の場合は識別子がユーザーなので、自分のID があればいいのですが、相手が人間ではなく情報機器の部品やセンサーで、複雑なアプリケーションを載せる場合は、Skype の方法では難しいのです。
v6 はすべてのものがつながるのが持論ですから、この挑戦は非常に大事だと思います。
これは、軍用のコミュニケーションでも非常に重要なことです。軍用の通信では、NAT の向こうがわからないのは、とても困るわけです。v6 であればNAT を使わず、すべてをコントロールできます。
また、全国に大量に導入して制御する必要があるIP 電話は、IPv6 でないと実現が難しいなど、ビジネスシーンでの必要性が認知されつつあります。IPv6 の未来や新しい価値の創造は、順調に発展していると思っています。
地球にトンネルを掘れ!?

――今後10 年のインターネットで、やるべきことはなんでしょうか?
●最近、米国に住むオンラインゲームユーザーがWIDE に連絡してきて、「お前のところで遅延があるからゲームに負けたんだ」と言われました。でも、米国から日本のサーバーにアクセスするのに理想的な速度を出すには、現状では光の速さを超えないと不可能なのです。
しかしそれは、発想を変えればできなくもない。ヨーロッパにいる人とIP 電話で話すのに、米国を経由すると300msecかかるが、ロシアを突っ切れば90msecで行くではないかということです。
こんなことは、インターネットを作ってきた10 年間考えたことはありませんでしたが、今は「地球にトンネルを掘る」ということも考えないといけないときかもしれません。そこまで考えに入れておかなければ、これからのインターネットに期待されることを満足させられないのです。
これは革命的なことです。これまで、「届けばいい」というインターネットのデザイン哲学を変えろというわけですから。しかし、こういったことはおもしろいチャレンジになりますね。遠いところには「穴を掘れ!」なんて。
――ありがとうございました。